1年生になって3回目の参観日。
今回は支援級での参観日だったので、(支援級は人数も少ないしゆったりクラスなので)息子も嫌がったり緊張している様子はありませんでした。
授業の様子
この日の授業は算数。
通っている支援級は人数が少なく他学年も含めて6人、先生は1人。なので授業の半分はプリントを解く自習時間、半分が授業と言った感じです。
前半の自習の時間ではプリント3枚出されていて、自分のペースでできるところまでやりましょうとプリントを前に並べていました。プリントは計算問題がぎっしり。その様子です。
・姿勢保持が難しい。じっと同じ姿勢で座り続けることがもともと難しいのは知っていましたが、やはりずっとゴソゴソ。プリントをしようと机には向かってるんですが、体を左右にゆらゆらゆらしてみたり、椅子の上で正座したり、机の横に立ったり。
・音が気になる。端の席の子が問題をすらすら解いて、「やった〜終わった〜」の声。その隣の子は教室内を立ち歩いたり、どんぐりのようなものをコンコンコンコン机に叩いて「ひゃ〜〜」と言いながら遊んだり。この音が気になって集中できない様子。だからと言って教室から飛び出すわけでもなく机に向かって、立ったり座ったりその場にいようと頑張っている姿。だからと言ってヘッドフォンをするのは拒否する息子。
・イライラ。最初の10分ほどは気が散りながらも頑張っていたのですが、音は気になるし問題がなかなか解けず、自分の中で3枚全部仕上げなければいけないという思い込み、参観日でいつもと違う環境。全部が重なって、「あーー!!」とイライラし始める。頑張って解いていたプリントも、途中から全部1、1、1、1、1、1、と殴り書きをして無理やり3枚のプリントを終わらせ自分の机の周りにまき散らす。
その後の後半の授業も、いつもだったら答えているようですが気持ちの立て直しができずずっとふてて名前を言われても全部拒否。授業が終わった瞬間に廊下を飛び出し、遠くの廊下の陰でうずくまって泣いていました。
息子への対応
1、とにかく気持ちを聞く。否定をしたり、教えたりするのでなく本人が話すことをいったん全部聞く。しかし現実では自分がイヤだったことをしっかり伝えることって結構難易度高め。この時の息子はカッとなっていてもう自分が何にイライラしているのかもわからなくなっている状態。そんな状態で話せるわけがないのでそっとそばにいること。
2、気持ちを代弁する。言葉にならない感情で「わー!!」とか「うー!!」とか言っていましたが、ちょっと声のボリュームが小さくなってきたり言葉数も少し減ってきた落ち着いてきたタイミングで、「イライラしたね」「苦しかったね」とおそらく感じているであろう感情を代弁して問いかける。当てはまってない声掛けには「違う」を返事してくれたりするので、「うん」か「違う」かで答えられるような声かけだと反応がしやすい様子。そこから何がイヤだったのかを本人と一緒に振り返り探していく。
3、できたことをしっかり褒める。授業中教室から飛び出さずに頑張ったことや、難しかったけど問題を解こうと少しの時間取り組めたこと、小さなことでも本人なりに頑張ったことをしっかり伝えて認めてあげること。できないことばかり本人は目を向けがちなので、本人は気づいていなくてもできたことろをしっかり伝えてあげると、自信につながる。
4、解決策を一緒に探す。イヤだった原因を一緒に見つけることができたら、次また同じことがあった時はどうする?を一緒に見つけていく。この時の息子の場合、プリントの問題が多すぎて解けなかったことに対してどうしたらいいかわからなくなったよう。そもそもまず先生が全部解けなくてもいいと説明していたので、説明をしっかり聞くこと。あとは解けないと思って困ってしまった時は、先生に聞いてみること。あとは計算ができるように家でも練習しようと3つ解決策を出しました。
その後の反応
パニックの状態から気持ちが落ち着くと共に徐々にこの対応を進めることで、息子自身も自分の気持ちの整理ができたのか教室へ戻ることができました。
その日の夜には、「今日の参観日、途中怒ってしまったけど最後まで頑張れたよね〜」と自分から振り返り話すことまでできました。
まとめ
教室を飛び出してから、気持ちが落ち着くまで約15分ほどかかりました。これはきっと個人差があります。
以前の息子はもっと時間がかかっていましたが、年齢が上がるにつれて色々な能力が上がってきたこともあるし、何よりこの過程を日々何度も繰り返しているから時間も短くなってきているのだと思います。
何度も何度も気持ちを聞いて、一緒に考えることを辛抱強く積み重ねること。これに尽きるなと感じます。
子育てをしながら、自分自身もこうやって一緒に成長していっているな〜と思う日々です。

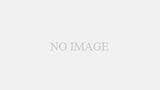
コメント